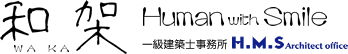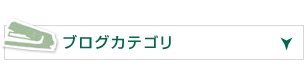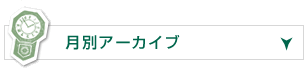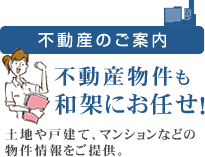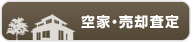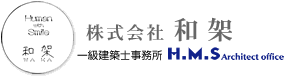ブログ
2022年7月別アーカイブ

夏季休業のお知らせ
2022年07月28日
平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます
弊社では誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます
■夏季休業期間
2022年8月11日(木)~8月16日(火)
休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次ご返答させていただきます
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます
→記事詳細ページ

上下水道の費用
2022年07月25日
皆さま、こんにちわ
ようやく夏本番という感じですね!
皆さまは「上水道口径別納付金」や「下水道受益者負担金」ってご存じですか?
なんだか漢字がたくさん並んでいて、よくわからないですよね。
土地を探されている方は、この言葉を見かけたことがあるかもしれませんね。
この2つは、土地に新しく水道を引き込む際にかかる費用です。
以前建物が建っていた場合を除き、売り出し中の土地には、上下水道やガス管などは基本的に引き込まれていません。
(土地情報には「前面道路配管あり」などの表記がされていることが多いです)
よってこのような土地に家を建てる場合、引き込み工事をしなければ水道が使えないというわけです。
引き込み工事費用のほかに必要となってくるのが、
上記の「上水道口径別納付金」、「下水道受益者負担金」です。
*****上水道口径別納付金について*****
上水道加入金とも呼ばれています。
上水道は口径(管の太さ)によって使用料も違ってくるんですが、
新しく使用開始する際にかかる費用も口径別に設定されています。
一般の住宅だと13㎜~20㎜の口径を使うことが多く、
鳥取市だと3㎜が42,900円、20㎜が119,900円となっています。(鳥取市水道事業給水条例より)
また、材料費や検査料も別途必要となります。
*****下水道受益者負担金について*****
原則は「公共下水道によって下水を排除できる地域内の土地所有者(受益者)」が支払います。
鳥取市の場合は、地域によって金額が異なります。
(詳しくはこちら、鳥取市のHPをご参照ください↓↓↓
下水道等使用料、負担金及び各種届出について|鳥取市 (tottori.lg.jp)
*****いつ、だれに支払うのか?*****
土地を購入する際に土地代と合わせて支払うことが多いです。
※購入予定の土地が分譲地であった場合、
売主である不動産会社などが立て替えている場合も多いです。
支払のタイミングや誰に支払えばいいのかは、確認が必要です。
→記事詳細ページ

不動産売買の流れ(買主様の場合)
2022年07月21日
皆さま、こんにちわ
ここ最近は雨が続いていますね。
梅雨明けはすでに発表されていますが、数か月後に訂正されることもあるんだとか。
降らないと困りますが、降り続くのも困りますよねー
本日は、「不動産売買の流れ(買主様の場合)」についてお話ししたいと思います。
売主様の流れについてはこちらの記事で説明してますので
ぜひ合わせて読んでみてください ↓↓↓
↓↓↓
不動産売却の流れ(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com)
*****探すまでにしておくこと*****
まずは、事前に決めておく、確認しておく方がよいことについてです。
・希望条件
住みたい地域(学校区など)、住み始めたい時期 など
土地であれば広さや形、住宅であれば新築or中古、間取り など
・予算
預貯金額の確認
住宅ローンを使うのであれば借入可能額の確認
(銀行に事前審査を申し込んでおくとスムーズです)
*****購入までの流れ*****
①不動産を探す
インターネットや折り込みのチラシなどを見てみる
また不動産会社に条件を伝えて、希望に合う物件を探してもらう
②見学する
希望に合った物件を見つけたら、実際に現地を確認します。
あらかじめ気になる点や疑問点をリストアップしておくと、見学しやすいと思います。
周辺環境のチェックも忘れずにしておきましょう。
③資金計画をたてる
物件探しと並行しながら、資金計画を具体化させていきましょう。
購入資金以外に必要となる経費やローンの金利、毎月の返済額などについても試算しておきます。
④購入の申し込みをする(買付証明書を出す)
購入の意思が固まったら、売主である不動産会社(売主が個人の場合は、媒介をしている不動産会社)に
購入の申し込みをします。*弊社は買付証明書を提出していただいております
⑤重要事項の説明を受ける
申し込みをした不動産会社の宅地建物取引士より、購入物件に関する重要事項の説明を受けます。
*難しい単語がたくさん出てきますが、大事な内容なのでしっかり聞いておきましょう
⑥不動産売買契約を結ぶ
重要事項説明を聞いて納得したら、売買契約を結びます。
この際、事前に決めておいた手付金あるいは契約金(物件価格の1割程度)を支払います。
契約書の内容は、重要事項説明と同じくしっかり確認しましょう。
ところで、契約書も重要事項説明書も署名押印を必要とする書面なんですが、違いをご存じでしょうか?
似たような説明をしている部分もありますが、役割は全く異なります。
契約書は、売主と買主がどういった条件で売買を約束したかを証明するものです。
売買価格や所有権移転の時期、契約解除の条件などの記載があります。
対して重要事項説明書は、購入物件がどういう物件なのかを説明するものです。
例えば、現所有者はだれか、広さがどのくらいあるのか、どういう場所にあるのかなどの説明があります。
この2つの書類は必ず、重要事項説明書→契約書の順で説明し、買主に署名捺印をもらわなければなりません。
なぜなら、不動産の売買では高額の金銭のやり取りがあり、
買主に(あるいは売主にも)十分な説明をして納得してもらってから、契約をする必要があるからです。
⑦住宅ローンの契約をする
ローンを利用する場合、売買契約を結んだあと住宅ローンの正式な契約をします。
売買契約書には「いつまでにローン承認を受けなければならないか」という項目があります。
なるべく早く必要書類を用意して、その日までに承認を受けられるようにしましょう。
⑧引渡しを受ける
決済日に残りの代金を支払います。
それと同時に、売主は物件を引渡し、不動産の登記手続きを行います。
*固定資産税・都市計画税の清算や仲介手数料の支払(媒介業者がいる場合)もこの時に行います。
*****まとめ*****
不動産売買時のポイントとして、
・条件に100%合う物件はなかなか無いことを知っておく
もちろん希望条件をすべて満たす物件が見つかるのが一番ですが、なにかしら妥協しないといけないことが多いのが不動産売買です。
時間に余裕があって、根気よく待てる方以外は、
希望条件の中で絶対に譲れない部分と、ここまでなら譲ってもいいという部分を作っておくと見つかりやすくなります。
・事前準備をしっかりしておくこと
不動産売買はタイミングが重要で、自分がいいなと思った物件は、他の人もいいなと思っていることがほとんどです。
住宅ローンの事前審査を受けておいたり、住宅メーカーを決めておいたり、
準備ができているかいないかの差で、2番手になってしまうこともあります。
せっかく見つけた物件を逃してしまわないよう、しっかりと準備しておきましょう。
・わからないことはどんどん聞く
不動産売買は高額な取引です。
聞いておけばよかった…と後から思わずに済むよう、気になったことはその場で確認するようにしましょう。
不動産会社はその場で答えられなくても、きっちり調べてくれます。
というのも、不動産会社には対象物件について調べる義務、説明する義務があり、
それが不十分だと処分を受ける可能性があるからです。*どうしても答えられないこともあります
ということで、不動産売買の流れについて説明させていただきました
大きな買い物なので慎重になってしまいますが、
自分がどういう生活をしていきたいか、イメージできる物件に出会えるといいですね
→記事詳細ページ

パントリー
2022年07月08日
皆さま、こんにちわ
昨日は七夕でしたね!
皆さまは何をお願いしましたか?
今回は、便利な収納の一つ、「パントリー」についてお話ししたいと思います。
キッチン周りってものが多くて、ごちゃごちゃしませんか?
毎日の家事に追われていると、きれいに保つのって大変ですよね…
そこで役に立つのが「パントリー」 最近はつけるおうちが増えてきましたね。
最近はつけるおうちが増えてきましたね。
パントリーを有効活用するために、メリット・デメリットをご紹介していきます!
*****パントリーとは*****
主にキッチンで使うものを収納するスペースのことです。
常温で保存できる食材、飲料や家電、食器などをストックする場所として使われます。
キッチンでの作業中に物を取り出しやすいよう、キッチン近くに配置されることがほとんどです。
棚のような奥行きが浅くコンパクトなものや、
出入口が2つあり、通り抜けられるようなウォークスルータイプ、
中を歩き回れる広さを確保したウォークインタイプなどがあります。
*****パントリーのメリット*****
・キッチンがすっきりする
キッチン内の収納だけでは足りず、手の届くところに置いておきたいがために、調味料などが出しっぱなしになりがち…
パントリーがあれば収納するスペースが増え、キッチン周りのものをすっきりしまっておけます。
また一般的には、扉(あるいはロールスクリーンなど)が付いていることがほとんどなので、
中身を隠しておけることもすっきりして見えるポイントです。
・買いだめできる
収納力が増えれば、いざという時に備えるための買いだめもできるようになります。
災害などがおきれば、普段通りに買い物に行くのは難しくなるので、家の中に備蓄しておけると安心です。
また、仕事などで忙しく、週末にまとめて買い物する方にもおすすめです。
*****デメリット*****
・パントリーをつくるための場所が必要
パントリーを作る=その分他のスペースがせまくなるということです。
またキッチン近くにあった方がいいので、空いたスペースに配置するわけにもいきません。
キッチンの動線を妨げないような位置と広さを確保する必要があります。
・使いにくいとストレスになる
たとえば、奥行きが広いパントリーを作っても、たくさん物を収納したときには奥のものが取り出しにくくなります。
また、棚が固定されていて無駄なスペースがうまれると、せっかくの収納も活用できていないことになります。
あらかじめ、何を収納したいのかをある程度決めておかなければならない、ということが分かります。
*****パントリーを作る際のポイント*****
スペースがあるからといってなんとなくパントリーを作ると、
せっかく増えた収納なのに使いにくい…ということになってしまいます。
パントリーを使いやすくするためのポイントとしては、
・棚の幅と奥行きを考える
幅も奥行きも広くとれば、もちろんその分収納量は増えます。 …が、
あまり幅を広くとると動線が長くなりすぎてしまい、奥行を広くとると奥のものが取り出しにくくなります。
棚タイプのパントリーなら、奥行きは30㎝~45㎝くらいにすると取り出しやすいでしょう。
またウォークスルー、ウォークインタイプなら設置する棚の奥行+60㎝以上の通路を確保すると動線がスムーズです。
・棚を可動式にする
収納するものはライフステージによって変化していきます。
固定式の棚は比較的丈夫で、重たいものをのせられるという利点がありますが、
将来、レイアウトを変えるときに不便に感じることもあるでしょう。
重たいものをのせられる棚は少なめにして、
残りを可動式の棚にしておけば、収納するものが変わっても調節できます。
*****まとめ*****
パントリーはとても使いやすく、キッチンをすっきりと保つことができる収納です。
しかし、作り方によっては反対に、無駄なスペースとなってしまうこともあります。
キッチンの使い方は人によって全然違うので、
パントリーを作る際は、自分だったらどこに何があると使いやすいのか、検討してみてくださいね
→記事詳細ページ

森の精
2022年07月04日
皆さま、こんにちわ
今週はあまりぱっとしない天気のようです。
梅雨が終わってから雨が降り続くことを「戻り梅雨」というそうですが、
実はこれから梅雨なんじゃないの…?と思ってしまいました。
先日、事務所の観葉植物に水やりをしていた際、あることに気づきました…。
なんと、森の精、トトロが遊びに来てくれていたんです!
なんとも言えない表情で遠くを見つめるトトロさん…。
居心地がいいのか、今のところ動かずにいてくれています 笑
→記事詳細ページ

吹き抜け
2022年07月01日
皆さまこんにちわ!
7月に入りましたね
先日、グーグルマップのストリートビューカメラカー(?)とすれ違って
ひょっとしたら私もストリートビューにのるんじゃないかとどきどきしています…!
さて、本日は「吹き抜け」についてお話していきたいと思います。
開放的でおしゃれな雰囲気のある吹き抜け。
あこがれている方も多いんじゃないでしょうか?
ただし、その憧れのままに吹き抜けをつくってしまうと、のちのち後悔する可能性が…。
メリット、デメリット、デメリットの解消法もあわせてご紹介します。
===吹き抜けとは?===
皆さまご存じだと思いますが、一応説明させていただきます。
吹き抜けとは、下層階の天井を抜いて、上層階とつなげた空間のことです。
主にリビングや玄関スペース、階段スペースに設けられます。
弊社施工のおうちの吹き抜けです。
===吹き抜けのメリット===
・開放感のある空間になる
縦に広い空間が吹き抜けの最大の特徴ですよね。
家族が長い期間を過ごすリビングに吹き抜けがあると、広々と居心地のいい空間になりそうですね。
・室内を明るくできる
吹き抜けがあると、通常よりも高い位置に窓を設置でき、太陽の光が入りやすくなります。
日当たり条件があまりよくない土地でも、吹き抜けによって解消できるかもしれません。
・風通しがよくなる
空気は下の窓から上の窓へと抜けていくので、家の中の空気が循環するようになります。
天井などにシーリングファンなどを設置すれば、さらに空気の通りがよくなります。
・家族とのコミュニケーションがとりやすくなる
2階、3階建てのおうちは、各界で空間が途切れやすくなります。
吹き抜けがあることにより、家族の存在を感じられ、声掛けもしやすくなります。
・デザイン性が高い
吹き抜けは日本にはもともとなかった造りなので、
それだけで海外のようなおしゃれな雰囲気を作り出せます。
2階部分まで見えることもあるので、きれいにしておこうと思えるのもメリットの一つかもしれませんね。
===デメリット===
・冷暖房効率が悪い
吹き抜け部分は広い分、快適な温度が分散してしまい、冷暖房が危機にくいのが欠点の1つ。
シーリングファンや床暖房などの設置、適切な換気システムの導入によって解消できるはずです。
・音・ニオイが気になる
良くも悪くも1階と2階が筒抜けになっているので、
リビングでのテレビの音や料理中のニオイが2階に届きやすくなります。
家族と生活時間が違うと、ストレスになる可能性もあります。
壁やドアを防音性の高いものにしたり、寝室をリビングから遠いところに配置したりという配慮が必要です。
・2階スペースがせまくなる
吹き抜けをつくるということは、2階の床がその分なくなるということです。
部屋数や収納スペースが制限されてしまうことも…。
間取りを工夫してスペースを確保しましょう。
===まとめ===
吹き抜けの吹き抜けのメリット・デメリットは、
たとえば「家族の存在を感じられる」=「生活音が聞こえる」のように表裏一体となっています。
建築の技術や断熱性能は日々進歩していて、
デメリットとしてあげた点も工夫すれば解決できることもあるでしょう。
おしゃれな家にしたいという憧れのまま、吹き抜けをつくることが目的となってしまわないよう、
吹き抜けをつくる目的が何なのか、おうちでどんな暮らしをしたいのかを
ご家族でしっかり話し合ってみてくださいね
→記事詳細ページ