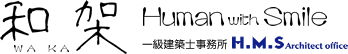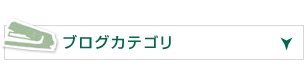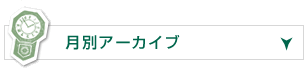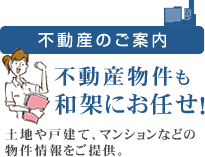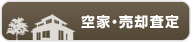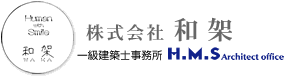ブログ
2021年12月別アーカイブ

もういくつ寝ると~...
2021年12月27日
皆さま、こんにちわ
いやー、降りましたねー
弊社事務所の前も真っ白になりました
12月にここまで降るのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか?
さて本年もあと1週間を切りまして、ブログ更新も今年最後となりました。
先日お知らせしたとおり、12/29(水)より冬季休暇をいただく予定となっております。
来年もなんとかペースを保って更新していきたいと思いますので
お時間あったら読んでいただけると嬉しいです
皆さま、本年は大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします
→記事詳細ページ

不動産売却の流れ
2021年12月23日
皆さまこんにちわ
本日は、不動産売買の流れ~売主様の場合~をお話ししたいと思います。
なんとなくの流れは想像できても、
どういう書類を用意するの?
事前に準備しておくことは?
売却後の税金ってどうなの? など実際にどうしたらいいのか分かりにくいですよね…
そこで、実際の流れに沿ってご説明していきたいと思います。
①不動産の査定
まずはいくらで売却できるかの査定をします。
無料で査定してくれる不動産会社もありますので、1社だけではなく、何社か査定をだしてもらうのもOKです。
弊社の場合は一度、売主様のお話をじっくり聞いてから査定をさせていただきます。
(不動産査定のご相談はこちらからどうぞ!!売却査定依頼・空き家情報提供 - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com)
電話でも承っております:TEL 0857-54-1147)
②媒介契約の締結
査定金額にご納得していただけたら、媒介契約書を作成し、媒介契約の締結をします。
※この時点で必ず必要というわけではありませんが、
固定資産税評価額がわかる書類をご用意いただけるとスムーズです。
③売却活動の開始
ホームページや情報サイトへの登録、お客様へのご紹介をしていきます。
※お持ちの不動産の境界が確定していなかったり、登記簿上の所有者が異なっていたり、
農地転用する必要がある場合はこの辺りから手続きを開始していきます。
④売買契約
買い手が見つかったら売買契約を行います。
契約書や重要事項説明書の説明を行い、売主様、買主様双方にご捺印いただきます。
※固定資産税については、1月1日時点での所有者に納税義務があります。
通常、一括・分割払いに関係なく、一旦売主様に支払っていただきます。
年間の固定資産税を日割り計算し、引渡し日以降の金額を決済時に合わせて買主様から頂く形がほとんどです。
⑤お引越し (売却物件が一戸建て、マンションやアパートで売主様がまだ居住中の場合)
※売買契約から引渡しまでは約1ヶ月ほど間があるのが通常ですが、
お片付けなどに時間がかかるようでしたら、あらかじめ契約書に引渡しの時期を指定しておくこともできます。
⑥決済・引渡し
買主様より売買代金が支払われたのを確認後、所有権移転の手続きをします。
手続きには数日かかりますが、代金が支払われた時点で所有権が移行したものとみなします。
また、仲介した不動産会社がある場合、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は受け取れる最大額が決まっていて、
・売買価格が200万円以下の場合→(売却価格×5%)+消費税
・売買価格が200万円越え~400万円以下の場合→(売買価格×4%+2万円)+消費税
・売買価格が400万円越えの場合→(売買価格×5%+6万円)+消費税
となっています。
⑦確定申告(売買した年の翌年の2月16日~3月15日)
不動産を売却し、(簡単に言うと)売った金額が買った金額を上回った場合、譲渡所得というものが発生します。
譲渡所得が発生すると、所得税、住民税、復興特別所得税が生じます。
上記の譲渡所得の求め方については、また後日お話ししたいと思います。
不動産売買は以上の流れで進めていきます。
いろいろなパターンがあり、売買にかかる期間は様々ですが、しっかりサポートさせていただきます
弊社は空き家、空地の売買仲介はもちろん、買取もさせていただいておりますので、
「そういえば、今使っていないこんな土地あったかも…」
「もう誰も住んでいないし、そろそろ実家の片づけしなきゃなぁ…」という方、
ぜひ一度、弊社にご相談ください
→記事詳細ページ

冬季休業日に関するお知らせ
2021年12月20日
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業日とさせていただきます。
2021年12月29日(水) ~ 2022年1月4日(火)
※期間中にお問合せいただきました件に関しましては、
1月5日(水)より順次ご対応させていただきます。
また、1月8日(土)を臨時休業日とさせていただきます。
皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
→記事詳細ページ

雪
2021年12月18日
皆さま、こんにちは
とっても寒いですね…
今年は12月に入っても、日中は割と暖かく感じていたので
ここまでの冷え込みを感じるのは今年初めてです
そして、初雪
皆さまのところはいかがですか?
風が強く吹いていたせいか、事務所周辺にはほぼ積もっていませんでしたが、
山側はけっこう積もったみたいですね
今年は例年に比べ、多く雪が降るそうです。
皆さま、運転にはぜひお気をつけください
→記事詳細ページ

洗面台
2021年12月13日
皆さま、こんにちわ
突然ですが、皆さまのおうちの洗面台、どこに置いてありますか?
我が家は玄関から脱衣所に行く途中の廊下に置いてあるんですが…
(昔ながらの古い一軒家なのでむだに広いのです )
)
最近のおうちで多いのは、脱衣所にあるパターン。
建売住宅ではよく見かける間取りですよね。
洗面台を脱衣所に置く理由として一番に挙げられるのは
「お風呂や洗濯機と同じ配管を利用できるから」という理由です。
これによって、取付が簡単になったりコストを抑えられるというメリットが出てきます。
できるだけコストを抑えたいという方は、なるべく水回りをまとめるといいかもしれません。
ただし、注意点もあります
まず、他のだれかが脱衣所を使用しているときに使いづらいことです。
お風呂に入っている方もタイミングを図ったりなんてこともあるかもしれません。
また、(トイレに手洗器がある場合を除いて)お客さんがトイレを使用した後、
脱衣所を見られてしまう可能性があることです。
水回りは特にプライベートな部分ですから、見せたくない方も多くいらっしゃるでしょう。
他に洗面台を置く場所として、どんなパターンがあるかというと、
トイレ横や玄関の近くなどがあげられます。
トイレ横だと、トイレの配管が使えるためコストが抑えられるほか、
わざわざ別室の洗面台に移動しなくてもよいといったメリットがあります。
また、玄関の近くに設置する場合は、
帰ってすぐ手洗うがいができる(コロナなど感染症の対策にもなりますね)、
出かける前に身だしなみチェックができることが魅力的です
ただし玄関はお客様をお迎えする場所なので、
洗面台を見えない場所に設置するか、ある程度デザイン性の高いものにするなどの工夫が必要かもしれません。
中にはメインの洗面台を脱衣所の中(もしくは近く)に設置して、
玄関や廊下、トイレ横などに小さい手洗ボウルのみをつけるという方もいらっしゃいます。
例えば弊社が設計、建築させていただいたおうちだと
メインの洗面台(おもにご家族でご使用されるもの)がこちら
トイレ横の手洗コーナー(お客様と共有部分)がこちら
ご家族の生活動線と分けることによって気兼ねなく使うことができます。
洗面台を置く場所としては、やはりライフスタイルに適した場所に置くのが一番です。
最近では奥行きが浅い洗面台なども出てきていますので、
家事動線や生活スタイルを想像し、洗面台をどこに置くか検討されてみてください
→記事詳細ページ

建蔽率と容積率
2021年12月09日
皆さま、こんにちわ
本日は建蔽(けんぺい)率と容積率についてお話したいと思います。
土地の売買をするとき、おうちを建てるとき、私たちが必ずチェックするものの一つです。
簡単に言ってしまうと、どちらも土地にどれだけの大きさの建物を建てられるかの比率のことです。
どういう違いがあるのかというと・・・
建蔽率は敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合です。
防火上と住環境配慮の目的があるといわれていて、
土地ごとに30~80%に設定されています。
建築基準法上、建蔽率を超える面積の建物は建てられません。
例えば、建蔽率60%の地域にある、100㎡の土地を買ったとします。
そうすると、この土地に建てられるのは建築面積が60㎡以下のおうちということになります。
(100㎡×60%=60㎡という計算です)
また、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合のことです。
容積率を設定することによって、建物の収容人数を制限し、
交通手段の確保や道路、公園、上下水道などの整備を効率的に行う目的があります。
こちらも土地によって50~500%の範囲で設定されています。
例えば、容積率200%の100㎡の土地だと、
延床面積200㎡以下のおうちを建てられることになります。
(100㎡×200%=200㎡という計算式になります)
建蔽率、容積率それぞれについて簡単に説明しましたが、
この2つの比率があることによって、敷地面積に対する建物の大きさを制限することができます。
建蔽率だけなら、建築面積だけ規定内におさめていればいくらでも高い建物を建てられることになってしまいますし、
容積率だけなら、理論上、敷地面積いっぱいの建築面積を持つ建物を建ててもよいことになります。
先日、用途地域についての記事をアップしましたが、
(用途地域①(ブログ) - 建築 設計事務所「和架」(鳥取県鳥取市) (waka-hms.com)
建物の性質などを統一するために、用途地域ごとに建蔽率、容積率が設定されていることがほとんどです。
実際には、指定されている建蔽率・容積率に加え、
角地による建蔽率の緩和や前面道路による容積率の制限などが該当する場合がありますので、
売買や建築をご検討の際は、事前にご確認をお願いします。
ということで、本日は建蔽率、容積率についてお話ししました。
お住みの地域がどの用途地域にあたるか気になる方は、「とっとり市地図情報サービス」と検索してみてください
「都市計画図」というページで、用途地域、建蔽率、容積率など確認できますよ
→記事詳細ページ