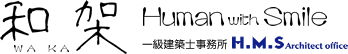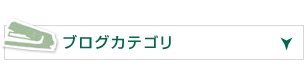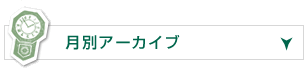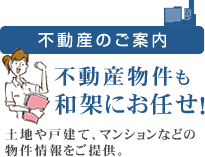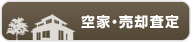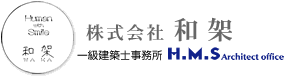ブログ
2021年9月別アーカイブ

用途地域②
2021年09月30日
皆さま、こんにちわ
台風の影響なのか、ここ数日少し蒸し暑く感じますね…。
さて、本日は用途地域についての第2弾をお届けします
どんな地域があって、どんな建物が建築できるのかをご説明したいと思います
ではまず、≪住居系≫から…。
①第1種低層住居専用地域
こちらの地域は低層住宅の環境を守ることを最優先としている地域です。
10mまたは12mの高さ制限があるほか、店舗、飲食店などは建築できません。
また診療所は建築できるものの、病院は建てられません。
一戸建て住宅が並ぶ閑静な住宅街をイメージしていただければ、と思います。
②第2種低層住居専用地域
こちらの地域にも10mまたは12mの高さ制限があり、高い建物は建てられません。
①との違いは150㎡までのスーパー、コンビニ、飲食店は建築できることです。
①と同じく閑静な住宅街を守りながら、生活面での便利さがある地域です。
③第1種中高層住居専用地域
この地域はマンションなどの中高層住宅の環境を守ることを最優先としている地域です。
飲食店やスーパーに加え、病院や大学なども建築可能ですが、オフィスビルは建てられません。
また高さ制限はありませんが、容積率の制限はあるため、
いくらでも高い建物が建てられるというわけではありません。
④第2種中高層住居専用地域
③に加え、2階建て以下、1500㎡までの大型店舗やオフィスビル、事務所の建築ができます。
こちらにも高さ制限はありませんが、容積率の制限がかかってきます。
⑤第1種住居地域
住居の環境を守るための地域ですが、①~④の地域よりも店舗等の建築の制限が緩和されている地域です。
3000㎡までの店舗、事務所、ホテルが建築できます。
ただし、カラオケボックスなどの騒音が予想されるものについては建てることができません。
⑥第2種住居地域
⑤と同じく、住居の環境を守る地域ではあるものの、建築可能な建物の種類がかなり多い地域です。
周辺の環境に配慮すれば、カラオケボックス、パチンコ店なども建てることができます。
⑦準住居地域
この地域は住居地域でありながら、幹線道路の利便性を活かすために、他の住居地域よりもあらゆる面で制限が緩和されている地域です。
そのため、自動車修理工場や車庫の建築もできます。
⑧田園住居地域
この地域は2019年4月にできた新しい地域です。
農業と調和した低層住宅の環境を守ることを目的としており、①と近い制限が課されています。
住居地域については⑧を除いて、数字が大きくなるにつれて、にぎやかになっていくイメージです
続きまして≪商業系≫ですが、こちらは2つに分かれています。
⑨近隣商業地域
周辺の住宅地に買い物などの場所を提供することが目的の地域です。
そのため周辺には住居系の地域があり、近隣商業地域内に住宅を建てることも可能です。
10000㎡までの店舗、飲食店を建築することができます。
ただし、周辺の住居系地域を守ることも目的としているため、キャバレーやナイトクラブは建てられません。
⑩商業地域
この地域は、商業の利便性を重視して開発していく地域です。
⑨では建築できないキャバレーやナイトクラブも建築でき、
オフィスビルや飲食店がならぶ、にぎやかな地域です。
住居系の地域より土地価格が高いことが多く、一戸建て住宅よりも高層のタワーマンションが建てられることが多いです。
最後に≪工業系≫です。こちらは3つに分類されます。
⑪準工業地域
主として環境悪化の恐れが少ない小規模工業の利便性を確保するための地域です。
工場の規模に制限はありませんが、騒音や火災、健康上の危険が予想される建物は建築できません。
工業系の地域に分類されていますが、マンションなどが並ぶことも多く、利用用途の幅が広い地域です。
⑫工業地域
この地域は工業の利便性を重視する地域です。
公害が発生する可能性のある工場も建築可能です。
そのため、住宅等を建てることもできますがほとんどなく、病院やホテル等の宿泊施設は建築できません。
⑬工業専用地域
工業業務の利便性を図るため、工場等の工業用建築物の専用地域です。
周辺住民に配慮する必要があり、工業用地としての利用を妨げる恐れがあるため、
住宅などは建築が禁じられています。
以上が用途地域の種類です。
いかがでしたか?
皆さまの土地探しに少しでも役立ちましたら嬉しいです
→記事詳細ページ

用途地域①
2021年09月27日
みなさま、こんにちわ
みなさまは「用途地域」という言葉を聞いたことがありますか?
土地をお探しの方は、見たり聞いたりされたことがあるかもしれません。
土地情報を見ていると、だいたい記載がありますよね
この「用途地域」は大まかに
≪住居系≫、≪商業系≫、≪工業系≫の3つに分けることができます。
そしてさらに細かく分類されているわけですが、
そもそも何のために分類されているのか、
どんな地域があるのか、簡単にご説明しようと思います
長くなりそうなので2回に分けますが、最後までお付き合いいただけるとうれしいです
それではまず、用途地域が何のためにあるのかをご説明します。
用途地域は住居、商業、工業それぞれの分野の環境を守っていけるよう設定されています。
例えば、
住宅街の中に突然、公害の発生する可能性がある工場が建ってしまったり、
工場と商業施設が近くにあった場合、商業施設の利用者で工場の流通がさえぎられてしまったり…なんてことにならないよう
ある程度住み分けをして、お互い良い環境を作っていこうねというものなんです。
とはいっても、商業系、工業系の地域の中でも条件があえばマンション等の住居を建てることもできますし、
住居系地域に商業施設や工場が建っていることもあります。
どの地域にどんなものが建築できるのか、は次回ご紹介したいと思います
それではまた
→記事詳細ページ

サツマイモ
2021年09月25日
皆さま、こんにちわ
先月はお休みしてしまいましたが、
今月のサツマイモ情報をお届けしたいと思います
8月の長雨にも強い日差しにも負けず、すくすくと育ち、
もう少しで収穫できそう…!というところまで来ました
地中にはたくさんのお芋が埋まっていることでしょう!
来月は収穫祭かな…?
→記事詳細ページ

旬のフルーツ
2021年09月14日
皆さま、こんにちわ
週末の台風(温帯低気圧?)、心配ですね
あまり大きな被害が出ないといいですが…。
さて、タイトルにもありますが、
この時期、鳥取で出回り始める果物といえば…
そうです、梨です
皆さまもう食べられましたか?
我が家では、ありがたいことに近所の方に毎年大量にいただくので、
もういいかな…と思うくらい毎日食卓に出現してます
十数年前までは祖母が梨を作っていましたが、高齢になり、やめてしまいました。
小学生のころ、梨の花に花粉を付けていたのを思い出します。
個人的には、二十世紀梨のように固めな梨が好きなんですが、
新甘泉やあたご梨など、果肉が柔らかめな梨もおいしいですよね
季節が変わるこの時期は、身体的にも精神的にもバランスが崩れやすくなるそうです。
おいしいものを食べて、体も心も整えましょう
→記事詳細ページ

玄関
2021年09月07日
皆さま、こんにちわ
9月に入りましたね!
日中はまだまだ暑いですが、夜はだいぶ涼しくなりました
本日は玄関戸についてお話ししたいと思います
家族が毎日使い、お客様をお迎えする場所ですから、
こだわりたい方も多いんじゃないでしょうか?
一般的に使われる玄関戸はおおまかに分けて2つ、
”引戸”と”開き戸”です
まずは引戸から…
引戸の玄関といえば、昔の日本家屋というイメージもあるかもしれません。
ですが、好んで引戸にされる方も増えてきています。
引戸には、
・引違戸→2枚以上の戸が重なっていて、左右どちらにも開閉できるタイプ(ふすまを想像していただければわかりやすいと思います)
・片引き戸→片方の壁にドアをスライドさせて開閉するタイプ(基本は1枚ですが、2,3枚連動している場合もあります)
・引き分け戸→真ん中から左右それぞれにスライドさせ開閉するタイプ(間口を広くとれる反面、横のスペースはかなり使います)
という種類があります。
引戸に共通しているメリットとして
・開け閉めしやすい→車いすの方やお年寄り、お子様など自分が動かず、スライドさせるだけでいいので開き戸に比べ、開閉がラクにできます。
・ドアを開けっぱなしにできる→荷物を持っているとき、ベビーカーを押すときには大変助かりますよね。
・玄関回りのスペースが不要→玄関回りに植物や置物をおいても邪魔になりません。
があげられますが、横のスペースが必要、気密性・断熱性が開き戸と比べ低いなどの欠点もあります。
続きまして、開き戸ですが
現代の日本住宅で多く使われているのが、この開き戸です。(マンションは特に多いですよね)
洋風な雰囲気を作りやすい扉でもあります。
開き戸には、
・片開き戸→ドアといえばこれ!というほど浸透してますよね。(ど〇でもドア~!のやつです)
・親子ドア→片開き戸に子扉を合わせたドア(子扉も開閉できるので、大きな荷物の搬入出もしやすいです)
・両開きドア→片開き戸2枚分の大きな開口が得られ、また重厚なイメージを演出できます。
という種類があります。
メリットとしては、
・気密性、断熱性が高い→開き戸に比べて開口部が少ないことが多く、ドアとドア枠もぴったりしている
・防犯性が高い→ドアとドア枠の隙間が開きにくいので、その分防犯性も高くなる
・デザインが豊富→最近は引戸も多くなってるが、比べると開き戸のほうが選択肢が多い
があげられます。
ただ、ドアの開閉が大変な場合もあることや、開けっ放しにしにくいなどのデメリットもあります。
引戸、開き戸どちらも魅力的ですが、玄関スペースによっては選べない場合もあります。
こだわりのある方はあらかじめ相談しておきましょう
→記事詳細ページ